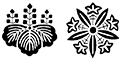当寺院について 当寺院について
私たちの想い
歴史を継承する寺院の歩み。
奈良時代の創建から再建、
そして未来へ。
奈良時代に聖武天皇の命によって、行基菩薩が派遣されてはじまった三河国分寺。過去に二度の火災に見舞われ、再建を重ねて現在の姿となりました。1975年(昭和50年)に曹洞宗の寺院として成り立ち、2007年(平成19年)から2009年(平成21年)に市教育委員会が実施した発掘調査によって、今の場所に新しい本堂が建て直されています。
もともと本堂を構えていた三河国分寺跡は、発掘調査は終えているものの、現在も歴史的な調査や研究が行われる重要な場所となっています。
寺院紹介
01 本堂
聖武天皇の詔(みことのり)によって創建された国分寺の法燈を受け継ぐ寺院で、古代の国分寺は10世紀後半頃に一度廃絶したとされています。しかし、その後16世紀に現国分寺が再興されました。再興された境内は、古代国分寺の跡地と重なっていましたが、現在はその位置が東方へと移されています。
02 国分寺瓦
建物に使用された瓦について、奈良時代の創建時のものが発掘されています。三河国分寺・国分尼寺跡では、屋根の軒先を飾る軒丸瓦は蓮華紋(れんげもん)、軒平瓦には均整唐草文(きんせいからくさもん)が採用されていました。発掘された軒丸瓦・軒平瓦は、創建期(8世紀半ばから後半)に使用されたものです。
03 本尊 薬師瑠璃光
ご本尊の薬師如来は、鎌倉時代から今に至るまで、当寺院に代々伝わるものです。愛知県の指定有形文化財としても登録されています。もとは八幡宮に祀られた像でしたが、神仏分離に伴い国分寺に譲渡されたと伝わっています。
04 銅鐘
1922年(大正11年)7月15日、重要文化財(国指定)に登録された銅鐘。八葉蓮華文の撞座の位置が高く、竜頭の向きが撞座の方向と直行することや、古式で竜頭の形や乳の配列・形が見受けられることから、平安時代前期につくられたものだと考えられています。
高さは118cmで下帯回りは256cm、口径は82.4cmで重さは678kg。竜頭の向きが撞座の向きと直交する古い形式で、乳は元80個のうち20数個を残しているそうですが、この乳の欠失については弁慶の引きずり伝説もあります。
05 永大供養塔
宗旨・宗派を問わずにご納骨いただける「永大供養塔」がございます。明るい場所に位置し、いつでもお花が絶えない穏やかな供養塔です。当寺院は歴史と伝統を重んじながら、現代の供養の形に合わせて大切に祈りの場を守り続けています。檀家様以外でもご納骨が可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
06 弘法大師像
極めて稀な「弘法大師様の生涯を描いた木像」もご覧になることが可能です。弘法大師様は幼名を真魚(まお)といい、5~6歳の頃には泥をこねれば仏像をつくり、「石を重ねれば塔婆にかたどる」などの伝承が残されています。幼い頃から非凡な才能を秘められていた、愛らしい真魚様のお姿をぜひご覧にいらしてください。
07 御朱印
御朱印は書置きを玄関にご用意しております。お参りのあとはどなたでもお持ちいただけますが、お持ちの際は心ばかりのご寄進をお願いいたします。ご希望の場合には御朱印帳にもお書きいたしますので、その際はお時間に余裕をもっていらしてください。
写真:国分寺十四世謹書
住職について
田中 信裕
- 経歴
- 15代目住職
ご供養のことでわからないことや相談したいことがある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ACCESS 交通案内
- 寺院名称
- 三河国分寺
- 電話受付
- 8:00~17:00
- 住所
- 〒442-0857
愛知県豊川市八幡町本郷31
- 電話番号
- 0533-87-2389
- 最寄駅
- 名鉄豊川線「八幡駅」より徒歩20分
名鉄豊川線「国府駅」より徒歩20分
- 駐車場
- 駐車場あり
※ご利用の方は事前にご連絡ください